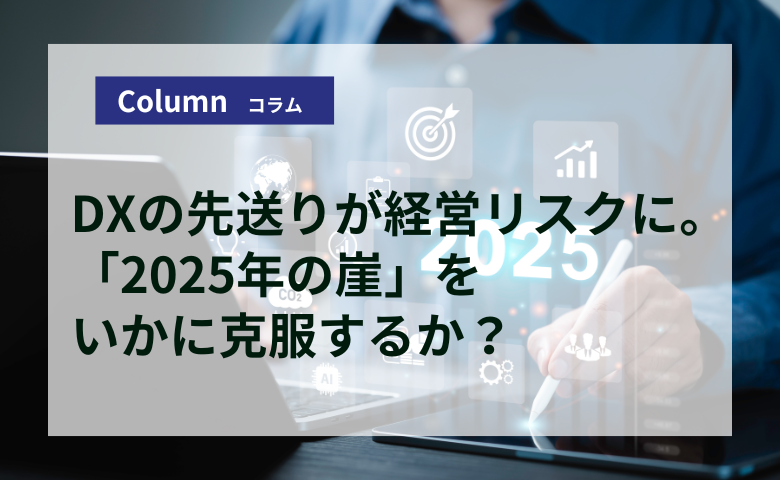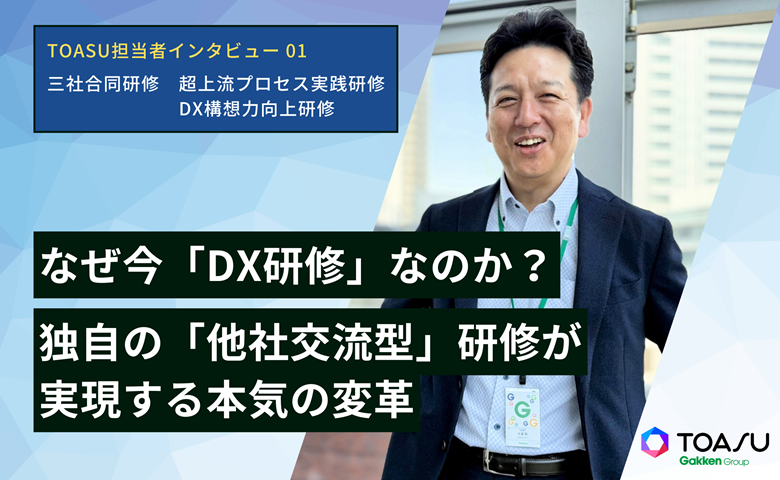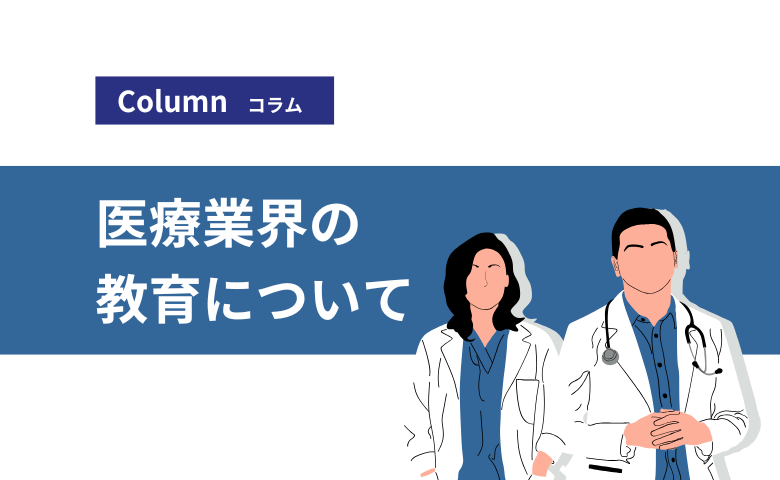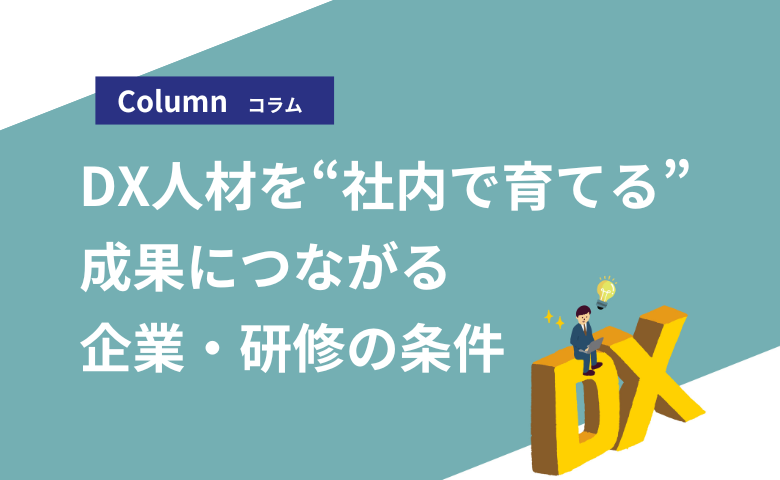COLUMN
研修コラム
「2025年の崖」という言葉をご存知でしょうか。
経済産業省が2018年に「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」内にて提示したキーワードで、複雑化・老朽化・肥大化・ブラックボックス化したシステム=レガシーシステムが残存することで、2025年以降最大12兆円/年にものぼる経済損失が出るという予測からきています。
これはDXと深い関係にあります。レガシーシステムの改善ができなければ、企業は世界的に爆発的な増加を続けるデータを活用しきれません。また、現システムの保守や運用、技術的負債による事故やリスクへの対処にソースを割いた結果、最先端のデジタル技術を担う人員工数を確保できない状況も起きています。
これらの課題がある状況ではDXを実現できない、それどころか今後の維持も厳しい。その限界を示すのが「2025年の崖」という提言です。
DXが進まない原因は?

DXが進まない原因について深掘りしてみましょう。
先でも紹介した「DXレポート」では、その原因のひとつを「レガシーシステムのブラックボックス化」としています。
根拠として稼働から21年以上経過した基幹系システムが6割にのぼること、そしてそれらのメインフレーム制作や保守を担っていた人員の退職・高齢化が進み複雑かつ不明瞭な現システムの維持・継承が困難になることを示しています。
また、そのような危機的なITの状況と経営戦略が連携できていないことも課題です。
DXの必要性に対する認識は高まっていても、実際に刷新すべきシステムの範囲はどこで必要な工数はどの程度か、今後どのようなデジタル技術をどう導入すべきか、どのようなデータをどのように活用するか、具体的な部分を判断しきれていない経営層が多いのが現状です。
そんな状況でただ「DX化を進めてください」、はたまた「生成AIを使って業務効率化してください」などと指示されても、経営方針が実行部隊に認識されていないため各事業部門の現場判断任せとなり、限定的な改革に留まってしまいます。
DX推進の具体的な対応策
改めて、DXとは「データとデジタル技術を活用して、製品・サービス・ビジネスモデルを変革すること」です。製品・サービス・ビジネスモデルを変えていくということは、当然ながら企業全体の課題となります。ただ「このシステムを刷新すれば」「データを整理すれば」というのはDXのX=トランスフォーメーションとは言えません。
つまりDXとは技術のみの話ではなく、人材と組織、経営の問題です。企業としてどのように新たなデジタル技術を活用してビジネスを変革していくか、経営層が明確に提示し主導する必要があるのです。
経済産業省はDX推進の対応策として、以下の5案を挙げています。
DX推進の対応策
1. 「見える化」指標、中立的な診断スキームの構築
経営者自らが、ITシステムの現状と問題点を把握し、適切にガバナンスする
2. 「DX推進システムガイドライン」の策定
既存システムの刷新や新たなデジタル技術を活用するにあたっての体制やプロセスを提示
3. DX実現に向けたIRTシステム構築におけるコスト・リスク低減のための対応策
実現すべきゴールイメージの共有、不要なシステムの廃棄・軽量化・細分化など
4. ユーザ企業・ベンダー企業間の新たな関係
システム再構築やアジャイル開発に適した契約ガイドラインの見直し
5. DX人材の育成・確保
事業部門人材のIT人材化、スキル標準・講座認定制度による人材育成
DX人材を育成・確保する
今回は先に挙げた対応策のうち、特に「5. DX人材の育成・確保」に注目してみます。DX人材とは、単にITスキルを持っているだけではなく、ビジネス理解・デジタル知識・変革推進力を持つ人材のことを指します。
ユーザ企業かベンダー企業かなど、企業や業務によって需要は多少異なりますが、例えば以下のような人材スキルが求められると考えられます。
・業務内容に精通し、ITで何を変革できるかを理解し、そのために求められる要件を明確にした上で設計、開発できる人材
・ユーザ起点でデザイン志向を活用し、UXを設計してまとめ上げる人材
・システムの刷新をビジネス変革につなげて経営改革を実現できるトップ人材
・スピーディに変化する最新のデジタル技術を詳しく理解し精通するITエンジニア
・AIの活用等ができる人材、データサイエンティスト
DXはトップと現場の両輪で

DXは世間の流行ではなく、今後企業が生き残っていくために行うべき変革のひとつです。そしてその変革は、DX推進の対応策でも示された通り「トップ自らのコミット」と「現場の育成・知識習得」を両輪で進める必要があります。なぜなら、レガシーシステムを刷新するのが最終的に人である以上、人が変わらなければ何も動かないからです。
まずはトップからリーダーシップを発揮していくことから始めましょう。実行への道筋を適切に整え、意思決定を明示し、社員を動かすのは経営層の役割です。
合わせて企業研修やリスキリングといった人材育成によって、現場の社員のDXへの理解と能力を高めていくことも大切です。DXを実際に経験できるような実地的な研修も増えていますし、次世代リーダーを育成する、ITリテラシーの基礎を学ばせる、といった研修で理解の底上げを目指すことも有効でしょう。
レガシーシステムは放置してはより負担が増していく一方です。今こそ、DXを理解し企業全体の戦略として取り組んでいきませんか。
経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf