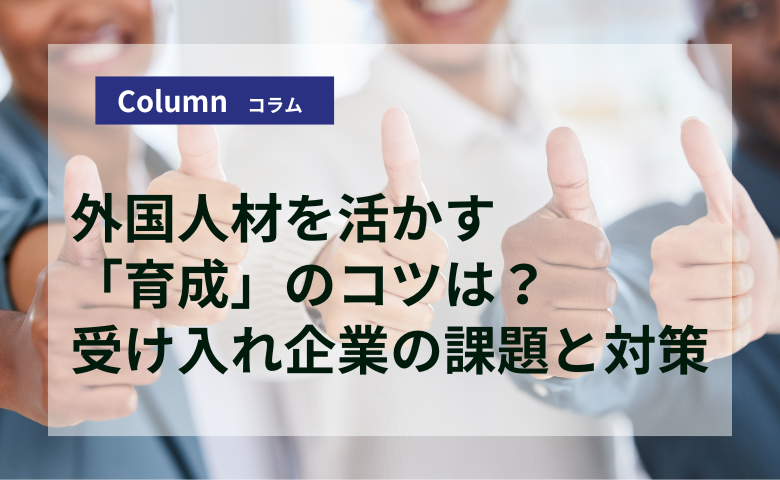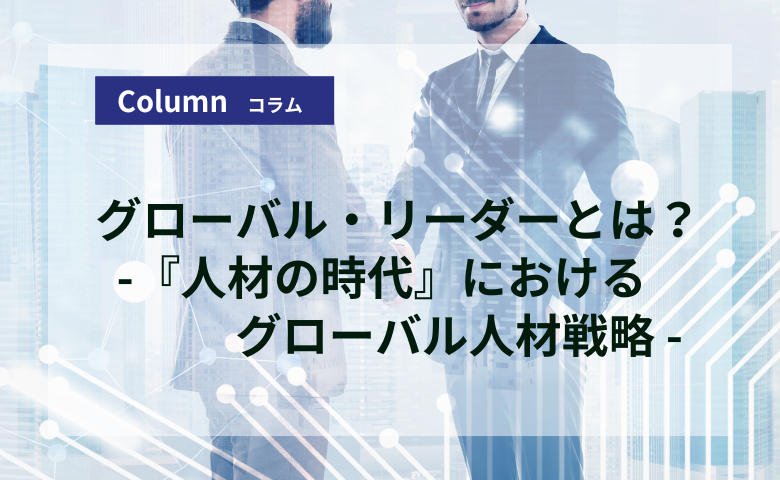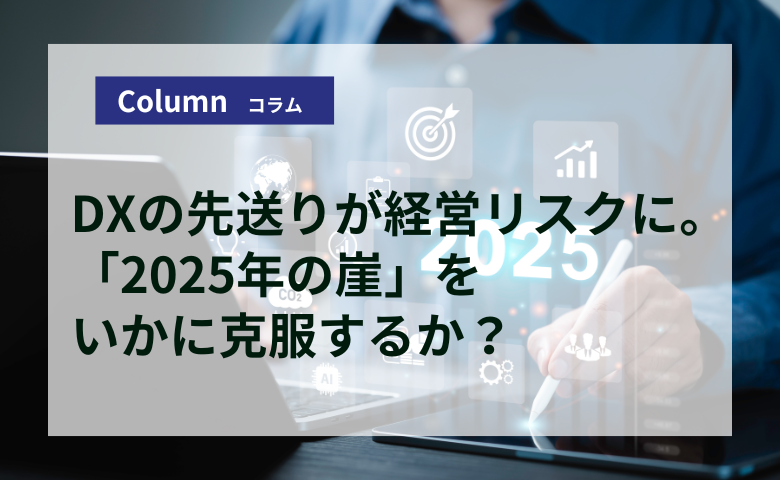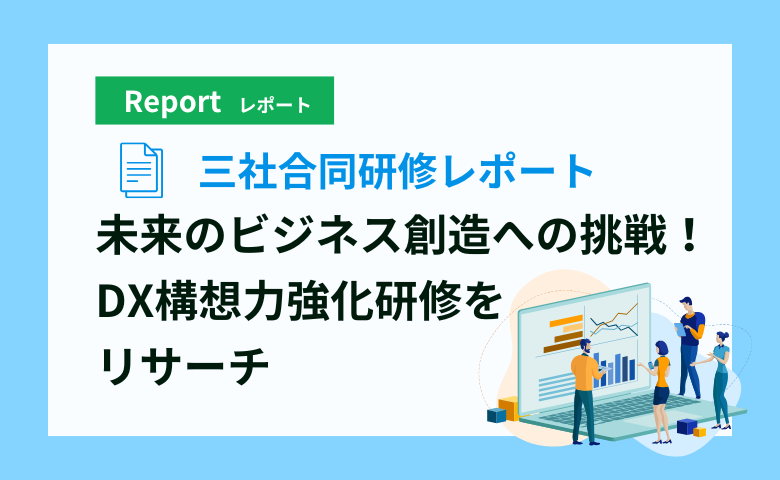COLUMN
研修コラム
人手不足が深刻化している現在の日本の労働市場。特定技能制度などの活用により、外国人労働者の受け入れを検討している企業も増えているのではないでしょうか。
外国人材とは外国籍を持ちながら日本で労働や専門的活動を行い社会経済に貢献する人々を指します。特に高度な能力や資質を有し一定の基準に達した外国人材は「高度外国人材」と認定されるなど、ただ労働力の補填目的だけではなく、海外市場の開拓やイノベーションの推進をも目的として、国家レベルで受け入れが促進されています。
しかし、外国人労働者の採用にあたっては多くの課題が存在します。たとえば、日本語能力の不足、業務理解の難しさ、文化的なギャップなどです。それらは企業の成長や、当事者である外国人労働者の職場への定着を阻害する大きな壁として立ちはだかります。
今回は厚生労働省や出入国在留管理庁の資料を基に、外国人就労の現状を明らかにした上で、今後企業が直面する課題と取り組むべき対策を検討していきます。
「外国人雇用状況」に見る数値
外国人の雇い入れ・離職の際には、氏名、在留資格、在留期間等を確認して厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出ることがすべての事業主に対して義務付けられています。それらを集計した厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況から見ていきましょう。
令和6年10月末の時点で、日本国内における外国人労働者数は230万2,587人。前年比で25万人ほど増加し、届出が義務化以降過去最多を更新しています。対前年増加率も12.4%と前年から同程度を保っており、外国人材の雇用の需要は依然高い水準と言えます。
産業別に見ると、最も多いのが製造業です。その後にはサービス業、卸売業・小売業が続きます。また増加率が高いのは医療・福祉分野で、2019年以降は前年比25%以上の伸びが続いています。
受け入れ後に重要なのは
増加を続ける外国人労働者ですが、その一方で重要な課題も浮き彫りになっています。特に今から雇用を検討している企業が注意すべきことは「受け入れた後」、つまり現場での「定着」と「育成」ではないでしょうか。
企業が外国人材の定着および育成を目指すにあたって、業務に関する研修・チューター制度以外では下記を両面で推進する必要があります。
- 明確な目標設定、およびそれに合わせた学習コースの設計
- 社内コミュニケーションを含めた生活・文化面での理解、支援
明確な目標設定、およびそれに合わせた学習コースの設計
まずは「明確な目標設定、およびそれに合わせた学習コースの設計」から説明していきます。
日本にやってくる外国人労働者の日本語能力はまちまちです。そして長く働くためには、入国後も学んで日本語能力を高め続けることが求められます。
たとえば新たに設けられる育成就労制度では、まず就労開始までに日本語能力A1相当(JLPTのN5等)以上の試験に合格、もしくはそれに相当する日本語講習の受講が必要です。そこから原則3年の間に技能検定基礎級等および日本語試験に合格しなければ、特定技能1号(在留期間5年)には転籍できません。
さらに在留期間の制限のない特定技能2号へ変更するには特定技能2号評価試験に加え、日本語能力B1相当(JLPTのN3等)以上の試験への合格が求められます。
企業としては当然、技術を身につけた人材には長く働いて欲しいもの。そのためには、企業側も協力して日本語学習の場を整えなければなりません。
スキルや今後の志望を参考にJLPTをはじめとした日本語試験の合格を目標に設定し、そのための体制作りや学習状況の管理を行う必要があります。業務と学習の両立に悩む外国人労働者が多い中、業務状況を鑑みながら学習スケジュールを設計できるのは、企業が主体となって行う場合の大きなメリットのひとつです。
社内コミュニケーションを含めた生活・文化面での理解、支援
続いて「社内コミュニケーションを含めた生活・文化面での理解、支援」ですが、こちらも企業側の積極的なコミットメントが重要となります。
つまり、外国人材に安心して働いてもらい、長く活躍してもらうためには、受け入れ時だけではなく継続的な支援が欠かせないということです。なぜなら、日本で暮らすにあたり、医療や子育て、教育、災害、社会参加など、業務以外の情報収集や把握に悩んだり、日本文化への理解不足や地域住民とのコミュニケーション障害から、孤立感を抱く外国人労働者が多いためです。
出入国在留管理庁が実施している在留外国人に対する基礎調査(令和6年度)でも、「あなたはどの程度、孤独であると感じますか」という質問に対し「しばしば・常にある」「ときどきある」「たまにある」と回答した人が合計で56.9%と半数を超えました。
意見・要望では「日常生活状況(鉄道、バス、銀行などの利用方法)から制度自体に至るまで様々な情報を含むと予想される短期集中講座が実施されると素晴らしいであろうと思う」「初めて日本に来た外国人に日本の習慣や文化、法令などを知ってもらうプログラムを実施すると効果がある」などといった情報提供の機会を望む声も複数見られました。
こういった課題を企業が解決・フォローできると、外国人労働者の企業に対するエンゲージメントも上がり、今後の活躍をより期待できます。
まとめ
ここまで日本にやってくる外国人材へ向けた取り組みを紹介してきましたが、受け入れる側、つまり日本の企業の学びも欠かせません。たとえば、日本人社員向けの異文化を理解する教育プログラムも効果的でしょう。
外国人労働者の状況をただ把握するだけでなく、職場で地道かつ積極的にコミュニケーションを取ること。その際にはお互い話しかけやすい雰囲気づくりや会話のきっかけづくりも重要になります。双方のバックグラウンドや価値観を尊重し、文化や考えを理解する努力も求められるでしょう。
社員の育成に投資することは企業の人材戦略に直結することであり、それは対象が日本人であっても外国人であっても変わりません。外国人労働者を企業内の育成対象として位置づけ、積極的に研修や生活の支援を継続していくこと。それがこれからの企業成長の大きなカギといえるでしょう。
※数値や状況は2025年5月時点のものです
厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001389442.pdf
厚生労働省「育成就労制度の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001301676.pdf
出入国在留管理庁「令和6年度 在留外国人に対する基礎調査」https://www.moj.go.jp/isa/content/001436042.pdf