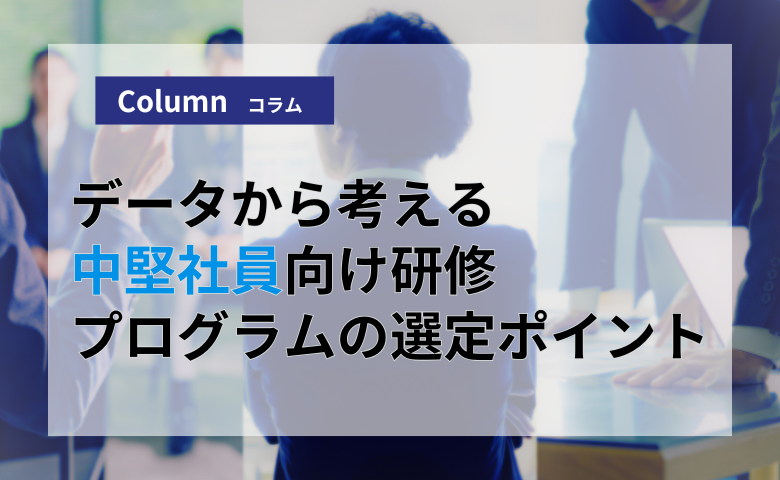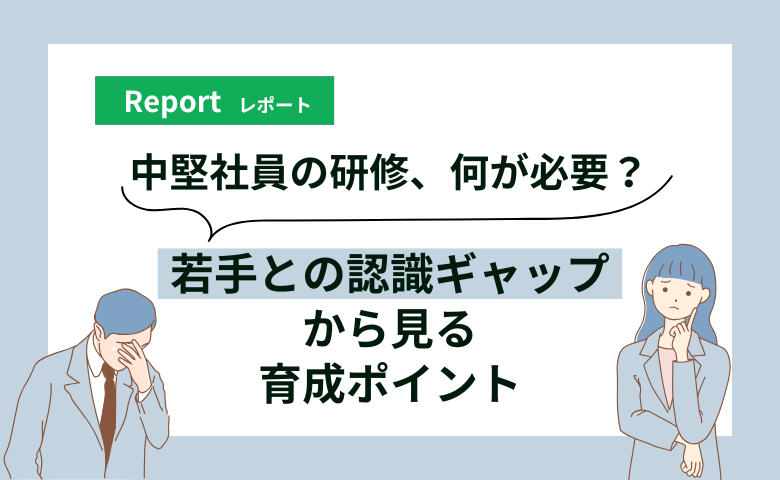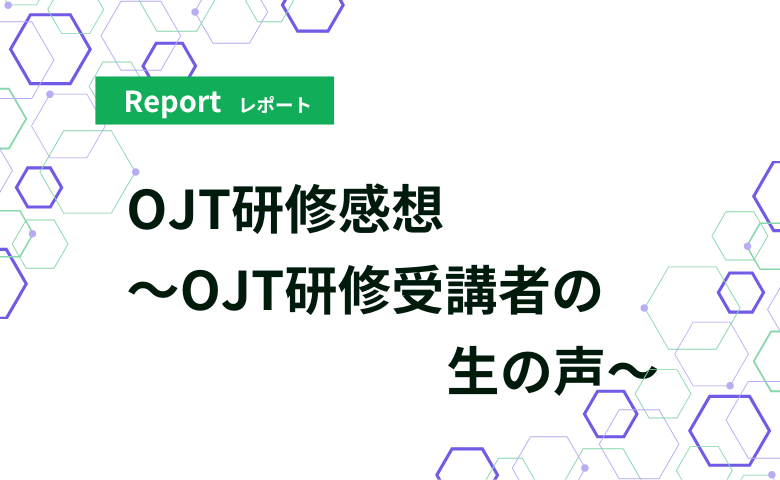COLUMN
研修コラム
企業の成長戦略において、近年ますます注目が集まっている中堅社員。新入社員ではない、けれど管理職層でもない、働き盛りかつ今後の企業の成長を担う世代である中堅社員ですが、育成という視点では後回しにされがちでもあります。
今回は2025年6月27日に厚生労働省が公開した「令和6年度能力開発基本調査」から、中堅社員の育成やキャリアの考え方、そして効果の高いプログラムの選び方などを模索します。
OJT・OFF-JTの現状

そもそも日本では実務経験を積み重ねて技能を習得するOJTが重視されてきた歴史があります。特に普段の業務をこなしながら見聞きし覚えていく「インフォーマルなOJT」が根強く、高度な技能形成に寄与する一方で定量的な評価や効果測定の難しさが指摘されてきました。また、研修などを含むOFF-JTは組織外の新たな知見・ノウハウを獲得することができるため、リスキリングの観点も含めて近年注目が高まっています。
※本コラム内では能力開発基本調査の「用語の説明」から、OJT=日常の業務に就きながら行われる教育訓練、OFF-JT=通常の仕事を一時的に離れて行う社内外の教育訓練(研修)、と定義する。
中堅社員向けの研修プログラムを考えるにあたって、まずは能力開発基本調査からOJTやOFF-JTの現状を確認してみましょう。
教育担当者、対象者、期間、内容などを具体的に定めて段階的・継続的に実施する「フォーマル(計画的)なOJT」を実施した事業所は全体の64.7%。コロナ禍突入後にやや割合が低下しましたが、近年は上昇傾向にあります。対象を階層別に見ると新入社員が54.7%、中堅社員が37.5%、管理職層が24.8%となりました。
一方でOFF-JTを実施した事業所の割合は73.8%で、こちらもコロナ禍のタイミングは縮小傾向にありましたが、現在は回復が見られます。職層別に見ると、新入社員が59.8%、中堅社員が57.1%、管理職層が51.0%でした。
OJTとOFF-JT、ともに階層が上がるにつれて割合が減るのは、やはりその内容が関係していると考えられます。実施したOFF-JTの内容は「新規採用者など初任層を対象とする研修」が75.4%と最も高い割合で、そこから大きく離れて「新たに中堅社員となった者を対象とする研修」(47.5%)、「マネジメント(管理・監督能力を高める内容など)」(46.6%)と続きます。
一方で、今後実施したいOFF-JTの内容は「新たに管理職となった者を対象とする研修」(35.4%)、「マネジメント(管理・監督能力を高める内容など)」(34.6%)、「新たに中堅社員となった者を対象とする研修」(32.4%)の順に高く、企業が中堅以上の社員に対してリーダーシップ・マネジメントスキルの育成意欲を持っているのを感じさせます。
キャリア開発支援の現状
続いて、キャリア開発支援の現状を見ていきます。
キャリアコンサルティングを行うしくみを導入している事業所は50.0%と半数。目的は「労働者の仕事に対する意識を高め、職場の活性化を図るため」「労働者の自己啓発を促すため」などの割合が上位を占めており、効果としても「労働者の仕事への意欲が高まった」「自己啓発する労働者が増えた」の割合が高く、目的に即した結果が得られていることがわかります。
一方で問題も明らかになっています。内訳としては「キャリアに関する相談を行っても、その効果が見えにくい」「労働者からのキャリアに関する相談件数が少ない」といった割合が高く、現場ではキャリアに関する課題の掬い上げに不足がある様子がうかがえます。
企業や社員がキャリアコンサルティングに対して不足を感じる要因のひとつとして考えられるのが、企業内のキャリアの相談体制です。
キャリアコンサルティングを行うしくみがある事業所のうち、相談を受ける相手がキャリアコンサルタントである割合はたった11.2%でした。実際に労働者がキャリアに関する相談をする主な組織・機関として割合がもっとも高かったのは「職場の上司・管理者」であり、つまり、上司がキャリア支援の能力を期待されていること、日々の業務における関係性や対話が部下のキャリア形成に大きな影響を与えていることを示しています。
この際、上司にキャリア開発に関する知識や能力がなければ、指導に不十分さや一貫性のなさ、偏りなどが含まれてしまい、部下のキャリアパス設計に不具合が生じる可能性があります。中堅以上の社員のキャリア支援能力を高めることは、組織全体のキャリア開発支援の質を向上させることにつながると言えます。
研修プログラムの選定ポイント

では実際に中堅社員向けの研修プログラムを検討する際、どのような観点で選べばよいのでしょうか。たとえば選定ポイントは以下の通りです。
ニーズの多様性への対応:一口に中堅社員といっても年次や持っている役割はそれぞれ異なります。ひとまとめに研修を行っても効果は出づらく、せっかく研修を行ったのに期待した結果が出なかった、ということになりかねません。
各社員の部署内での役割やキャリアパス、組織と個人それぞれの課題など、テーマに応じた研修プログラムが求められます。
新たに中堅社員となった者への特化:特に新入社員の期間を終えたばかりの入社後3・4年目の中堅社員に対しては、役割が変わったことを認識させるための研修を行うことをおすすめします。新しいポジションで行うべき業務、持つべき思考、身につけるべき振る舞いなど不可欠な基礎を築き、スムーズなキャリア移行を支援しましょう。
リーダーシップ開発の準備:チームを牽引する機会が増える中堅社員にとって、メンバーを指導する能力は特に習得すべきスキルとなってきます。上司として、さらには将来の管理職としての役割を担うための準備ができるよう、リーダーシップの理解やコーチングスキルの習得などの研修の機会をキャリアパスと連動する形で設けるべきです。
OJTの質の向上:中堅社員以上の「計画的なOJT」が手薄くなりがちなのはデータにて述べた通りです。固定的に行われる制度・内容にできるかを含めて整備を進めることを意識しましょう。
また計画的以外、普段の業務上でのOJTやフィードバックについても、より成長と生産性向上に寄与する内容へ日々改善していく姿勢を忘れないことが大切です。
一社研修、合同研修、公開型研修、eラーニング……学習の形態はさまざまあります。それぞれのメリット・デメリットを上記のポイントと掛け合わせて検討しましょう。
また組織開発の観点から、自己啓発支援の充実やキャリアアップ・スキルマップのサポート制度なども並行させるとさらに効果を高めることができます。育成計画はきちんと筋道立てて行い、かつ定期的な見直しも合わせましょう。インストラクショナルデザインなど専門的な目線を取り入れてより効果を向上させることもおすすめです。
厚生労働省「令和6年度能力開発基本調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/104-06b.pdf